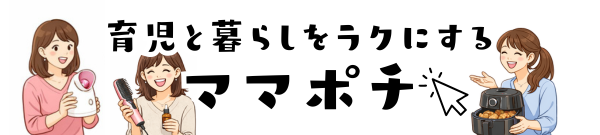ギャルママ
ギャルママ絵本作家のぶみって今何してるの?
かつて話題作を次々と発表し、テレビや書店でも注目を集めた彼ですが、最近ではメディア露出が減り、現在の活動が知りたいと感じている人も多いようです。
結論、
現在は絵本作家として絵本を出版しつつYouTubeで胎内記憶の子供やニュース・都市伝説や予言などの発信をしています。
▶のぶみさんのYouTubeチャンネルはこちら
また、オンラインサロンなどでファンと深い交流を行ったりと新たな新境地へ進んでいます。
この記事では、のぶみさんの今の活動内容やSNS・YouTubeでの発信、過去の炎上の背景、そして現在のファンからの支持のあり方まで、幅広く掘り下げてご紹介します。



彼の作品を子どもに読ませたいと考えている親御さんにとっても、安心材料になる情報をしっかりとお届けしますね。
また、



以前の炎上は現在の活動に影響しているのか?
なぜ今も絵本が売れ続けている?
なども気になる方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。
\ 子どもに人気!?胎内記憶図鑑 /
絵本作家のぶみ現在の活動とは?
絵本制作と出版活動の継続
のぶみは現在も精力的に絵本を制作し続けています。これまでに280冊以上の絵本を世に送り出しており、その勢いは今も衰えていません。
絵本というジャンルの中で、親子の絆や命の尊さをテーマにした物語を多く手がけており、新作も継続的にリリースされています。
また、出版社との関係も健在で、大手出版社からの新刊発行も確認されています。彼の作品は読者層が広く、子どもだけでなく親世代からの共感も多いため、今なお書店や図書館で高い人気を保っています。
さらに、イベントや講演の場でも絵本の読み聞かせを行うことがあり、単なる作家活動にとどまらず、直接子どもたちに向けた表現者としての活動も行っているようです。
YouTubeでの発信とその特徴
のぶみは公式YouTubeチャンネル「絵本作家のぶみチャンネル」を運営しており、こちらも現在の主要な活動のひとつです。2024年時点でチャンネル登録者数は17万人を超え、総再生回数は3,900万回を突破しているなど、その注目度の高さがうかがえます。
チャンネルでは、絵本の読み聞かせ動画に加え、子育てに関する考え方、作品の裏話、自身の人生経験なども語っており、ファンや親世代からの支持を集めています。表現方法として動画を取り入れている点も、現代的な発信スタイルといえるでしょう。
特に、自らの声で絵本を読むことで、作品世界をよりリアルに伝える工夫が見られます。また、ライブ配信などでファンとの交流も行っており、作家と読者がつながる場としても機能しているのが印象的です。
活動内容の変化と今後の展望
以前はテレビ番組やイベント登壇など、よりマスメディア寄りの活動が多かったのぶみですが、現在はYouTubeやSNSを中心としたデジタル発信へとシフトしています。この変化は、彼のメッセージをよりダイレクトに伝える手段として機能しているようです。
一方で、過去の論争を受けてメディアへの露出は抑え気味になっている可能性もあります。しかしそれでも、自主的な発信を続けることで、自分の言葉で読者と向き合う姿勢を保ち続けている点は注目に値します。
今後はオンラインとリアルの両方を活用しながら、講演活動や絵本制作により力を入れていくと予想されます。自身の経験を語りながら、次世代に伝えていく活動がさらに広がるかもしれませんね。
YouTubeチャンネルで見るのぶみの発信力
動画のジャンルと視聴者層
のぶみのYouTubeチャンネルでは、絵本の読み聞かせを中心に、子育てに関する持論や創作の裏側について語るコンテンツが多く投稿されています。絵本作家としての顔だけでなく、ひとりの父親、人生の先輩としての視点も垣間見える内容です。
視聴者層は主に30代〜40代の親世代が中心で、子どもと一緒に動画を観ている家庭も少なくありません。そのため、単に子ども向けというよりも、親子の時間を大切にするツールとして活用されている印象です。
また、動画の中では自身の失敗談や迷いについても正直に語っており、肩肘張らずに楽しめる点が魅力です。視聴者との距離が近いのも、のぶみ流の「伝え方」なのでしょう。
登録者数と再生回数の推移
2020年にスタートしたYouTube活動は、コツコツと積み重ねた投稿によって着実に伸びています。
2024年時点でメインチャンネルの登録者は17万人を超え、サブチャンネルでも約9,000人がフォローしています。
総再生回数も3,900万回以上に達しており、特に人気の読み聞かせ動画や育児トークは多くの反響を得ています。子どもの反応を見てから登録したという保護者も少なくないようです。
数字の推移だけを見ると、爆発的ヒットというよりは、着実に支持層を広げている印象です。
短期的ではなく、長く愛されるスタイルで視聴者を獲得している点が特徴的といえるでしょう。
親子に向けたメッセージの発信
のぶみのYouTubeには「親子の時間を大切にしてほしい」「もっと子どもを抱きしめてあげて」といったメッセージがたびたび登場します。
動画の合間にも、彼のそうした思いがあふれているのが印象的です。
彼は自身の経験から、「親からの愛情が子どもの自己肯定感に大きく関わる」と語っており、その考えは絵本にも動画にも一貫して表れています。
とくに、子どもが悲しみや不安を感じたときの対応についての言葉は、多くの親に響いているようです。
このように、動画は単なるエンタメとしてではなく、のぶみなりの教育的な意味合いを持った発信ツールとなっています。
だからこそ、リピーターが多く、ファン層が安定しているのかもしれませんね。
代表作から見る絵本作家としての軌跡
長年の作家活動と転機
のぶみは1990年代から絵本制作を始め、現在までに280冊以上の絵本を出版してきました。絵本作家として長いキャリアを築く中で、さまざまなテーマや表現技法に挑戦し続けてきた姿勢が、多くの読者に支持されています。
初期のころは比較的ポップでユニークな作風が多かったものの、ある時期を境に「命」「親子の愛情」「死と向き合う心」など、より深いテーマに向き合う作品が目立つようになりました。その転機のひとつが『ママがおばけになっちゃった!』シリーズのヒットです。
このような作品を通じて、子どもにとっての身近な悲しみや戸惑いをやさしく伝える作風へとシフトしたのは、作家としての成長と経験が影響しているのかもしれません。
人気シリーズに込めた想い
のぶみの代表作といえば、『ぼく、仮面ライダーになる!』や『ママがおばけになっちゃった!』が挙げられます。いずれも50万部以上の発行部数を記録しており、子どもたちの心をがっちり掴んだ人気シリーズです。
これらの作品に共通するのは、「子ども目線で世界を見る」という一貫した姿勢。たとえば仮面ライダーになりたいという夢を通じて自己肯定感を育んだり、ママの死という重たいテーマをやさしく描くことで、子どもの心に寄り添う構成がなされています。
特に後者は、泣きながら読み聞かせる親も多く、家族の時間に温かさをもたらす作品として、今も多くの家庭で読まれ続けています。
絵本に反映された人生経験
のぶみは過去にいじめ、不登校、非行などの経験を公表しており、それが作品に深みを与える大きな要素となっています。自伝的要素のある語り口は、読者にリアリティと信頼感を与えているのかもしれません。
また、少年時代の寂しさや葛藤を乗り越えた体験が、子どもの痛みに寄り添う感性へとつながっている点も見逃せません。彼の絵本には「君のままで大丈夫だよ」というメッセージがたびたび登場し、これは人生経験から導き出された言葉でしょう。
そうした背景を知ったうえで作品を読むと、単なるストーリーにとどまらず、のぶみの人生そのものがにじんで見えてくるはずです。
のぶみの人物像と社会的評価
SNS発言をめぐる論争とその影響
のぶみはこれまでにSNS上での発言がたびたび話題になり、その一部が論争を巻き起こしたこともあります。特に育児や障がいに関する表現には賛否が分かれ、一部メディアで批判的に取り上げられたことも記憶に新しいでしょう。
また、2021年には東京五輪の文化プログラムから辞退する事態に発展したこともあり、作家としての活動に影響を与えた可能性もあります。ただし、全ての意見が否定的だったわけではなく、むしろ「本音を言える人」として支持する声もありました。
このように、表現者としての姿勢が常に注目を集めてきたのぶみは、炎上のリスクを恐れずに自らの想いを発信し続けているといえます。
メディアでの扱われ方と世間の反応
一連の論争以降、のぶみのメディア露出は以前より減少傾向にあるようです。そのため「最近見かけなくなった」と感じる人も多いかもしれませんね。
一方で、本人はYouTubeやイベントなど、自主的なメディアを通じて情報発信を続けており、メディアに頼らない活動スタイルを確立しつつあるようです。これは現代の作家にとって大きな強みともいえるでしょう。
テレビや新聞といった従来型メディアに縛られず、自分の言葉で自分の思いを届けたいという姿勢が、現在の活動方針に表れているのかもしれません。
ファンからの支持と評価の二極化
のぶみは一部から批判を受ける一方で、長年にわたって熱烈な支持を受け続けている作家でもあります。とくにファン層は、彼の絵本に救われたという読者や、子どもとの会話のきっかけになったという親たちが多いようです。
このように、好き嫌いがはっきり分かれる人物であることは否めませんが、それもまた「表現者としての個性」が際立っている証拠と言えるかもしれません。作品に感動する人が多い一方で、意見の分かれる点があるのは当然のことです。
結果的に、評価の二極化そのものが、のぶみという作家の存在感をより強くしているともいえるでしょう。
なぜ今ものぶみの絵本は読まれ続けるのか
共感を生むテーマ設定
のぶみの絵本が多くの家庭で読み継がれている理由の一つに、「共感しやすいテーマ設定」があります。
親子、命、夢、喪失感といった人生の核心に関わる題材を、子どもの目線で描いていることが読者の心をつかんで離しません。
たとえば、突然ママがいなくなったという設定の『ママがおばけになっちゃった!』は、悲しみをやさしく受け止めるための物語として評価されています。
多くの親が「うちの子が泣きながら聞いていた」と語るように、感情移入しやすい作りになっているのが特徴です。
その一方で、のぶみ自身の実体験や悩みを投影しているからこそ、リアリティがあり、説得力のあるストーリーが生まれているともいえるでしょう。
親子の会話を促すストーリー
のぶみの絵本には、子どもが感じたことを親に伝えたくなるような仕掛けがたくさんあります。単に読んで終わりではなく、「このときどう思った?」「ママだったらどうする?」といった会話のきっかけを自然に生み出します。
それが家庭内でのコミュニケーションを豊かにし、絵本が家族の絆を深めるツールとして機能するのです。実際に、「のぶみの絵本を読んでから子どもとよく話すようになった」という声も多く聞かれます。
このように、単なる娯楽ではなく、親子関係を育む媒介として絵本を捉えている点も、彼の作品が読み続けられる大きな理由の一つといえるでしょう。
読者の心に残る言葉の力
のぶみの作品には、印象的なセリフや一言がたびたび登場します。
「ママはいつでもきみのそばにいるよ」「そのままのきみでいいんだよ」など、心に響く言葉が子どもにも大人にも届きます。
こうした言葉の力は、何気ない日常の中で読者に寄り添ってくれる存在となり、繰り返し読みたくなる理由にもなっています。
SNSなどで名言が引用されることも多く、その影響力は紙面の中にとどまりません。
心に残るメッセージ性を持つ作品は、流行に流されず長く支持されるもの。のぶみの絵本が今もなお読まれ続けているのは、こうした「言葉の力」が根底にあるからかもしれません。
ここまで、絵本作家のぶみの現在について、活動状況やYouTubeでの発信、代表作に込められた思い、そして論争の背景やファンからの支持の現状に至るまで幅広くご紹介してきました。絵本作家としての彼の歩みと変化を通じて、今なお多くの人に読まれ続ける理由が見えてきたのではないでしょうか。
この記事を執筆しながら感じたのは、のぶみという人物の表現には一貫して「誰かの心に寄り添いたい」という想いがあることです。作品の中で語られるメッセージ、発信される言葉の一つひとつが、誰かの人生の節目や日常に寄り添っている──それが彼の活動の原動力であり続けているように感じました。
本記事が、のぶみという作家への理解を深めるきっかけとなり、彼の絵本を新たな視点で楽しむヒントになれば幸いです。
もし、あなたが子どもとの時間をもっと大切にしたい、絵本を通して親子のつながりを深めたいと考えているなら、のぶみの絵本にもう一度触れてみてください。